技術広報の集い #4 に参加してきた #技術広報の集い

2024/05/18(RubyKaigi 2024 Day4)、沖縄県那覇市で開催された「技術広報の集い #4」に参加してきました。
RubyKaigiの興奮(とふつかよい)も覚めやらぬDay 4、ふとSNSを眺めたら開催に気がついたので、昼ビールの予定を変更してエントリーしたのでした。
会場
RubyKaigiでもコワーキングスペースとして提供されていた、さくらインターネットの「SAKURA innobase Okinawa」で開催されました。どーんと広くて机と椅子とホワイトボード、スクリーンと音響機器、インターネットとバーカウンターまである。イベント会場として最高の環境でした。
そういえばコロナ禍以降、コミュニティイベントに場所を貸してくれる企業が激減してしまいました。情勢が情勢なのでしかたないのですが、古の勉強会だいすきエンジニアとしてはさびしい限りです。なので、こうやって会場提供してくれるさくらインターネットさんには感謝です。
じつは前日の昼間にもちょっとだけ仕事をしにお邪魔していたのでした。ありがたい。
イベント
前半はLT5本、後半は3テーブルに分かれてディスカッション、という構成でした。雰囲気はTogetterを見るとなんとなくつかめるかもしれません。
LTは参加者の事例についての発表で、具体的にやったことや苦労が聞ける貴重な機会でした。どこもみんな苦労しているけど、その苦労のポイントは違うのでな…。
グループワークは事前にディスカッションしたい課題を付箋に書いておき、それをテーブルホストが選んでファシリテーションする、という構成でした。
- 技術広報としてのキャリア
- カンファレンスに参加したメンバーの幸福度アップ
- 技術広報タスクのスケールアップ / アウト
…などのテーマに参加していろいろ聞いたりちょっと喋ったりして、たいへん有意義な時間を過ごせました。昼ビールしてる場合じゃなかった!参加できてよかった!
技術広報というおしごと
コロナ禍以降のRubyKaigiなどカンファレンスを見ていると、技術広報という(DevRelと呼ばれることも増えた)仕事に、若い方がたくさん取り組むようになったな、という印象を受けます。聞いた話ではエンジニアとして採用された新卒社員が希望することもあるとか…。
オーガナイザーの法林さんとも話したのですが、ぼくらがエンジニアとしてキャリアをスタートしたころには存在しなかった仕事ですから、先行事例の共有がまだまだ不足していますし、先輩もあんまりいない。さまざまな不安とちょっとした期待が入り混じったキャリア感があるのかな、と思っています。
いわゆる普通の広報と違って、成果や利益を可視化するのが難しい仕事でもあります。成果としてわかりやすい「採用」は結果が出てくるタイミングを読めませんし、業務の過程においては「組織開発」の側面も強くあります。会社や組織の中にも外にも働きかけていく必要があり、いろんな種類のコミュニケーション能力が要求されます。
そっかー若い人が悩みを抱えているのか。じゃあ経験だけはたっぷりもってるので、助けになってあげたいな。そういう気持ちになる時間でもありました。
宣伝と次回予告
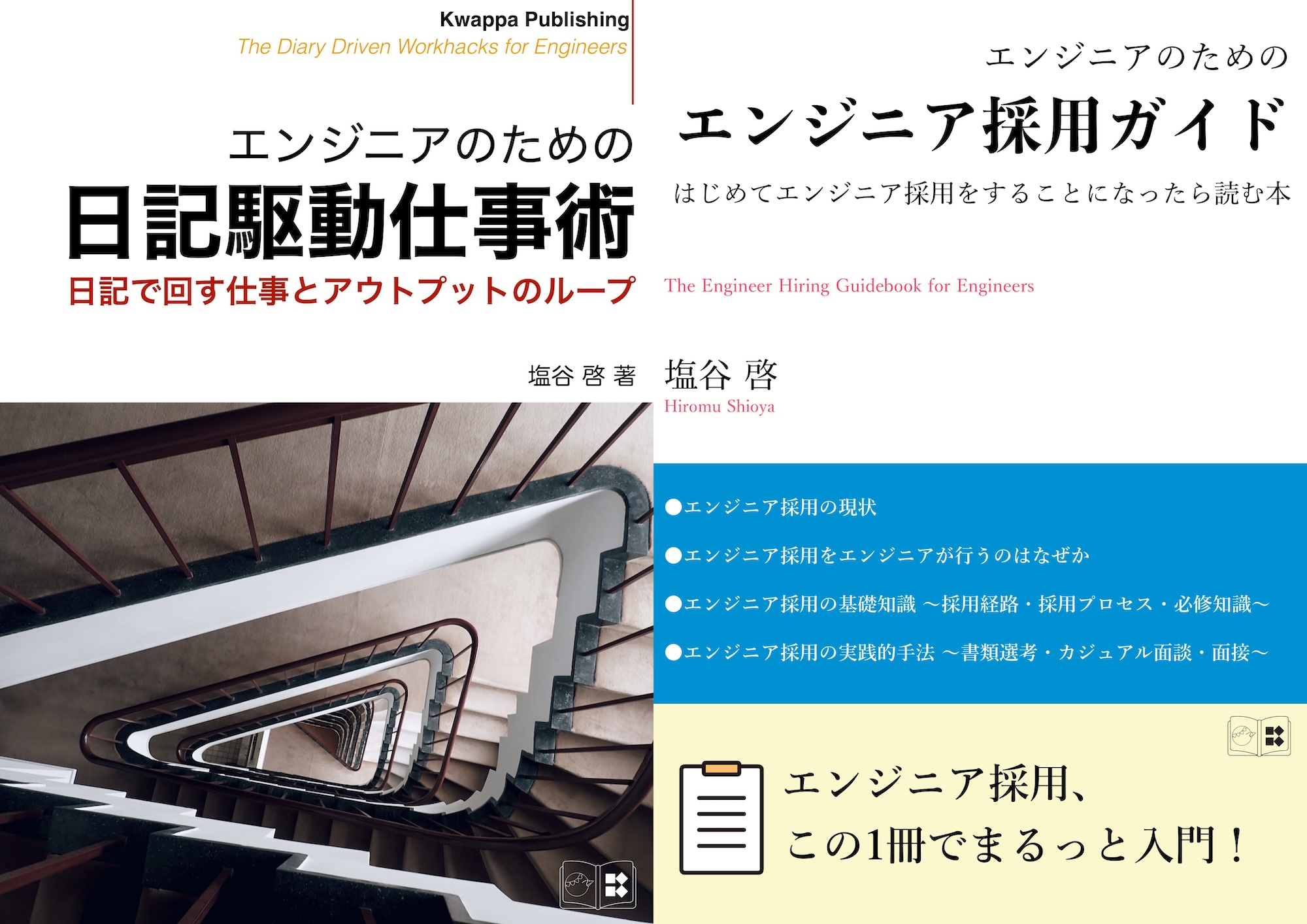
昨年の技術書典15で「メタエンジニアリング 理論と実践、その未来」という同人誌を頒布しました。技術広報・採用・組織開発を「メタエンジニアリング」と名付け、エンジニアリングの知識と経験を活かして、組織と個人の生産性向上に寄与していく活動を紹介した書籍です。
技術広報は採用にも組織開発にも密接に関連がある仕事ですから、メタエンジニアリングとして各領域のつながりを把握し、現場や経営との関係を理解していく一助としておすすめします。
そして、5/26に開催される技術書典16では、「日記駆動仕事術」と「エンジニア採用ガイド」という2冊の新刊を頒布します。
「日記駆動仕事術」には、ブログなどエンジニアとしてのアウトプットを効率的に行うメソッドを紹介しています。エンジニアにブログを書いてもらうのは技術広報にとって重要な仕事ですから、役立ててもらえれば幸いです。
「エンジニア採用ガイド」には、タイトル通りエンジニアがエンジニア採用をするときに必要な知識を詰め込んであります。技術広報の成果として「採用」は最も需要なもののひとつですから、ノウハウを知っておくことはプラスになるはずです。
イベントの最後に、「東京での開催を計画中です」「運営が不足しています」という話がありました。なので、次回はイベントそのものをお手伝いしようかなと思っています。悩める技術広報のみなさんは、技術広報コミュニティ - connpassのメンバーになっておくと開催をキャッチしやすくなります。
いろいろたいへんなこともあると思うけど、技術広報は重要で、そして楽しい仕事です。そこに携わる人には、どうせならできるだけ楽しく、そして将来のキャリアのプラスになるような経験をしてほしいと思っています。そのためのお手伝いを、微力ながら続けていければな、という決意表明の記事でもありました。